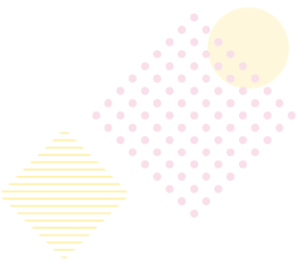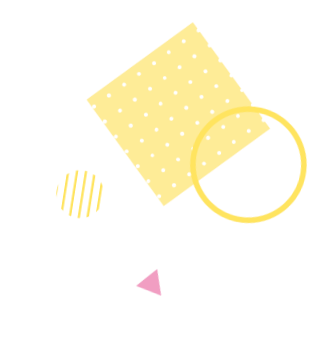取材:記事/RanRanEntertainment 写真/RanRanEntertainment・オフィシャル
世界に日本の「Anison(アニソン)」を躍進させた開拓者であり、“レジェンド”と称されるスーパーユニット「JAM Project(JAPAN ANIMATIONSONG MAKERS PROJECT)」の結成20周年を記念した、キャリア初のドキュメンタリー映画『GET OVER -JAM Project THE MOVIE-』が2月26日(金)より公開される。本作では2019年の結成記念LIVEから約460日間にわたって長期密着を敢行。レコーディング、海外LIVE、LIVEツアーリハーサルを通し、ありのままのJAM Projectの姿を映し出す。本作のメガホンを取った大澤嘉工監督に、密着を通して感じたJAM Projectの思いを語ってもらった。

大澤嘉工監督
――今回、どういった経緯で密着がスタートしたのですか?
プロデューサーからのオファーです。ドキュメンタリーは、この人いいなと思って、自分から調べて企画を出す場合と、プロデューサーなどからオファーを受けて撮影する場合がありますが、今回は、オファーを受けて、ゼロからスタートしました。それはどちらがいい、悪いというものではありませんが、僕の経験では、信頼がある人からオファーを受けて撮影する方が最終的に良いものになる率が高いように思います(笑)。
――自分の企画だと、思い入れが強すぎるということもあるのかもしれませんね。
そうなんですよ。僕はドキュメンタリーは、関係性や距離感を撮るものだと思っているんです。その距離感は、演者と僕たちの、それから今回ならば彼ら一人ひとりのアニソンに対する距離もあります。それは常に変化するものなので、その距離を測定して、映像として残すのがドキュメンタリーだと思うんです。よくドキュメンタリーというと、それが真実かどうかということに焦点が当たりますが、そんなものはどっちでもないんです。編集した時点で何らかの意図が加わるものですから。そこにあるのは、その関係性の距離感。そこに、もしかしたら真実みたいなものが宿る可能性はあるかもしれません。なので、今回は、彼らの名前くらいしか知らないところから、2年近くの時間をかけて撮影したことで、5人の距離やカメラと彼らの距離といったものが、うまく融合することができたんじゃないかと思います。
――撮影中、JAM Projectのメンバーが持っているパワーや熱量を感じた瞬間は?
(JAM Projectのメンバーは)それぞれがシンガーとして、自立して立っている人たちです。でも、5人が集まった瞬間、それが凝縮されるんです。決して融合しないであろう5つの個性豊かなピースが、ガチャンと見事にハマってきれいな球体になる。それを感じたのが、ライブの最初の声を出す瞬間でした。そこにパワーがあるのかなという気がしました。

――劇中にもライブのシーンが出てきますね。本作を鑑賞して、ライブは彼らの活動において大きな要素だと感じました。実際にその熱狂を目の当たりにされて、監督はどう感じましたか?
でも、実は(本作において)ライブシーンは、3回しか撮影していないんですよ。
――確かにそうでした。ですが、ものすごく印象に残っています。
そうなんです。それが彼らのパワーで、彼らの真骨頂だと思います。まあ、単純にステージは撮っていて格好いいですからね(笑)。一人ひとりの表情もそうですし、5ショットにしたときの画もそうですが。演者のすごさを感じられるのは、まさにライブだと思います。ライブって、「LIVE」と書きますよね。「オープニングで生まれて、エンディングで1回死ぬ」くらいの気持ちで彼らもやっているのだと思いますし、それがステージに表れていることを感じました。

――海外での盛り上がりもすごかったですね。
本当にすごかったですよ。コンベンションセンターでの盛り上がりを見て、ひょっとしたら文化というものは、国籍や肌の色などを横断的に越えられる可能性があるのかもしれないと感じました。普段、差異とされているものも、アニソンという一つの文化によってシェアできるんじゃないかな、と。それくらいのパワーを感じました。例えば、日本のミュージシャンが海外で公演しても、ファンがその歌詞を日本語で歌うことはあまりないと思うんですよ。でも、彼らのファンは、普通に日本語で歌うんです。それはとてつもないことだと思います。映画の中で福山(芳樹)さんが「小さい頃にロックに憧れて、意味も分からずに歌詞を耳で覚えて歌っていた」という状況の逆のことが起きているんです。

――劇中には、メンバーへのインタビューシーンもありましたが、彼らの言葉で印象に残っていることを教えてください。
具体的な言葉ではなく、インタビュー全体を通して感じたことですが…。皆さん、必死で自分の居場所を探す旅を、歌とともにしているんだなと感じたことが強く印象に残っています。でも、そうして居場所が見つかったからといって一筋縄ではいかなくて、壁があったり、傷が残ったりする。それは、音楽のことかもしれないし、人生においてかもしれない。ひょっとしたら、新型コロナによってその居場所が揺れたり、失われたのかもしれない。そうやって色々なことが起きるけれども、彼らは自分の居場所を探す戦いをずっとしてきていて、インタビューでは、そのことを語ってくれたんだと思います。例えば、遠藤(正明)さんが「アニソンなんてダサいと思っていた。でも、ここが俺の歌うべき場所だ」というようなお話をしていますが、まさに居場所を探すということを象徴している言葉だと思いました。

――なるほど。その居場所を探す戦いは、アニソンだから、歌手だからということではなく、誰にでも共感できるお話ですね。
はい、どんな職業でもそうでしょうし、ひょっとしたら人が生きるということは自分の居場所を見つけることなのかもしれないとも思います。でも、見つけた居場所は必ずしも安全なわけではなく、次に行かなければいけない時もある。新型コロナのように社会的に大きな出来事があったり、辛いこともいっぱいある。逆に言えば、居場所が発見できると人は安心できるとも思います。彼らの話は、きっとそういうことだったんだろうなと、今になって感じています。

――先ほど、「ドキュメンタリーは関係性や距離感を撮るものだ」というお話がありましたが、その距離感はどのようにして詰めていくのですか?
それは肌感覚でしかないので、言葉で伝えるのは難しいですね…。本作では、最初のレコーディングシーンは、トータルで2週間以上撮影したのですが、よく観ていただくと主観の画はないんですよ。密着を始めてすぐの撮影でしたし、僕自身、距離が詰まっていないのに無理に(距離が)詰めたものを撮るつもりもなかったので、ああいった画になっているわけです。映像で見ても、そこから徐々に(距離が)近づいていっているのがわかると思います。密着を始めてから半年経った頃にロングインタビューを行う予定だったので、その頃には心根を聞ける距離感になっていたいと思って、徐々に信頼関係を築いていこうと思って撮影していました。人の出会いと一緒ですよ。

――最初の段階で、たくさん話して一気に距離を詰めるというわけではないんですね。
僕の場合は徐々にですね。まずはカメラに慣れていただくことが先だと思っているので、最初は個人的な話はほとんどしていません。どんなにプロの方でも、ドキュメンタリーの密着となると身構えてしまうところがあるんです。カメラはやはり異物なので、その異物を自然なものに感じてもらうためにはやっぱり時間もかけなくてはいけない。なぜかそこにいるのが当たり前という状態にしないと、素に近いものはなかなか出ないんです。
――なるほど。では、今回は、約2年間に渡る撮影期間の、かなり長い時間を密着に費やしているんですね。
そうですね。もちろん、常にというわけではありませんが、ニューヨークにも一緒に行きましたし、濃密なところは撮っていると思います。
――撮影していて、一番印象に残ったシーンはどのシーンですか?
ニューヨークの居酒屋です。あの時、初めてガシッと通じ合ったんですよ。彼らが、カメラに対して心を開いた瞬間だったと思います。
――それは、やはりニューヨークだったからこそ、開放的になったということなんですか?
そうですね、海外だったからこそということもあったでしょうし、ライブ後の打ち上げだったので、その高揚感があったということもあると思います。でも、そこにいくまでに、種を丁寧に植えて、陽に当てて水をやってきたものが、ポコンと発芽したという感覚がありました。
――その感覚が、監督にとってドキュメンタリーを撮る時の醍醐味ですか?
撮影に関してはそうですね。それは演者さんがプロの方でも、例えば職人さんなどの一般の方でも関係なくて、「この作品の主役になった」という瞬間があるんです。それが撮影できた時、この作品はいけると思うんですよ。それが、今回はニューヨークの夜だったんだと思います。
――作品によってはその瞬間が訪れない場合もあるんですか?
それはありますよ。初対面で、撮影できる期間が短ければ、やはりなかなか難しいですね。
――初対面の場合は、撮影前にどの程度、演者のことを調べてから密着するんですか?
僕は、骨格くらいしか調べません。調べすぎてしまうとバイアスがかかってしまうので、対峙した時のイメージを大事にしたいんです。その方がミスリードすることもないと思います。対峙して、同じ空気を吸っていると、一緒にいることが自然になっていく…というような感覚です。

――彼らの表現してるものを、バイアスを通さずに見るということですね。
そうです。あと、アホみたいな話ですが(笑)、作品が決めていくんですよ。僕じゃないんです。編集作業で、次はどのカットでその次はと、映像を繋げていく時に、僕が決めているんじゃないという感覚がすごくあるんですよ。逆に、そこまでいかないとあまりいいものにならないのかもしれない。自分のエゴで作っているような作品は大したものにならないんです。
――貴重なお話をありがとうございました。改めて、本作の公開楽しみにされてるファンの方たちに、一言メッセージを。
ぜひ劇場でという言葉を言いづらい世間の状況ではありますが、特別な空間を体感していただけると思います。今回、ドキュメンタリーとしては珍しく7.1chです。この作品は、「観る」というよりも「体験」できる作品だと思います。ぜひ「体験」しに来ていただけたらと思います。

『GET OVER -JAM Project THE MOVIE-』
出演:JAM Project
影山ヒロノブ 遠藤正明 きただにひろし 奥井雅美 福山芳樹
Guest Artist:ALI PROJECT angela GRANRODEO FLOW 梶浦由記
監督:大澤嘉工
製作:井上俊次 二宮清隆/企画:松村起代子 宇田川美雪/プロデューサー:高橋義人/撮影:脇屋弘太郎 西岡章/録音・音響デザイン:石寺健一/オンライン編集:波江野剛/ラインプロデューサー:安養寺紗季 原啓介/制作:東北新社/配給:東宝映像事業部
2021年/日本/カラー/16:9/114分
http://Jamproject-movie.jamjamsite.com
(C)2021「GET OVER -JAM Project THE MOVIE-」FILM PARTNERS