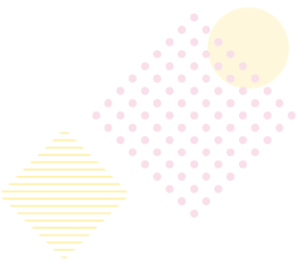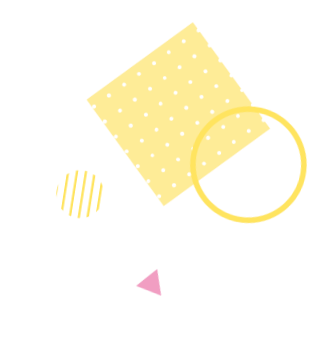取材:記事・写真/RanRanEntertainment
2019年5月から6月に「メ~テレ」で放送されたドラマ「ヴィレヴァン!」が、『リトル・サブカル・ウォーズ 〜ヴィレヴァン!の逆襲〜』として映画化され、10月23日より上映される。
ドラマ「ヴィレヴァン!」は、名古屋が生んだ、遊べる本屋「ヴィレッジヴァンガード」を舞台に、自称「空っぽ」の杉下とその仲間たちが過ごしたハチャメチャで刺激的な青春の日々を描いたドラマ。深夜放送ながら、サブカル好きの心に火をつけ、カルト的な人気を誇った。今回の映画版では、壮大なスケールで主人公・杉下たちの壮絶なバトルが描かれる。
今回は、後藤庸介監督と、脚本のいながききよたか氏に本作誕生の経緯やサブカルへの思いを聞いた。

いながききよたか(脚本) 後藤庸介 監督
――ドラマ版では、「ヴィレッジヴァンガード」で働く主人公たちの日常とも呼べる日々や、お店の裏側が描かれていました。今回は、そこから一転して、映画ならではのスケールの大きなストーリーになりましたね。
後藤庸介監督:実は、最初は映画ではなく、ドラマの続編をやるつもりだったんです。ありがたいことに、ドラマが好評をいただいていたので、ドラマをたっぷりとやらせていただこうと思って打ち合わせにきたら「映画をやりましょう」って(笑)。
――それは想定内のお話だったんですか?
後藤:いや、全く(笑)。
いながききよたか氏:好評をいただいていたとは言っても、本屋さんの話なんで。
後藤:ただ本屋の話だもんね(笑)。まあ、僕たちも冗談では確かに言ってましたよ。「映画やるとしたらどうしましょうか?」って。
いながき:映画の話を聞いても、最初はドラマの総集編のような形で、良いシーンを集めてつないで、最後だけ新しく撮影したシーンが入る形を想像していたんですが、話し合いをしているうちに「せっかく映画化するなら面白いものを」ってなっていって…。監督、覚えてます(笑)?
後藤:あはは(笑)。いながきさんは、もともと映画を作られている方ですが、僕はドラマ畑なんですよ。でも、映画が大好き。だから、普段は作らない「映画をやりましょう」って言われたら、「ドラマにはドラマの良さがあるけれど、あれは日常の点描スケッチだから、映画にするわけにはいかない」って。映画は芸術作品だからと、なんだか色々と考えてしまったんですよね(笑)。もちろん、芸術がというような高尚なものにするつもりはなかったのですが、意味があるものにはしたかったんです。
いながき:そうですね。結局、ヴィレヴァンさんのお話なので、面白いことから発想していった方がいいと考えて、いい意味での「パクリ」、もっと高尚に言うのであれば「オマージュ」といったものが良いのではないかと思いました。ヴィレヴァンさんの店内のように、好きなもので埋め尽くされた映画でいいんじゃないか、と。
後藤:意味はあるものにしたいけれど、格好つけたくはなかったんで、最初から、ジャンルものにしたいなと思ってたんです。どのジャンルにするのかは、その時点では決めていませんでしたが、でも映画らしく「ジャンルもの」で、しっかりと尖った表現の強いものにしたいということを話していました。

後藤庸介 監督
――なるほど。スタートは「ジャンル映画」だったんですね。
いながき:そうですね。最初は、発想の源として、ジャンル映画を念頭に置いてました。それこそホラーやアクションの、既存のストーリーをうまく利用しながら、そこに新しいもの絡めていくという感覚から始まったんだと思います。
後藤:「パクリ」というと言葉が悪いのかもしれませんが、僕は「サブカルは、メジャーがあってこそのサブカルだ」というテーマが好きなので、たくさんの方が知っているメジャーな作品の胸をうまく借りて、面白く作り上げるということを、恥ずかしげもなくやりたいと思っていました。まあそうやって、いろいろと組み合わせていったら、結果的に、全ジャンル入った作品になってしまったのですが(笑)。
――(笑)。それでも、最初は何らかの、限定された「ジャンルもの」から発想が広がっていったわけですよね?
いながき:ヴィレヴァンさんのイオンモール名古屋茶屋でロケができることになっていたので、そこをうまく利用して作れないかということを考えたときに、SFが良いんじゃないか、と。
後藤:SFなら、時を繰り返すことで、同じ場所、同じシチュエーションで何回でもできるからね(笑)。
いながき:そう(笑)。これは、タイムリープものだ! って(笑)。それで、初稿の段階では、がっつりとタイムリープの話にしていました。でも、その後に監督と話をしながら本を書いていくうちに、こういう要素もある、こんなのもあると、いい意味でタイムリープを抜いていった。
後藤:ジャンルものであるということと同時に、別軸ではこの映画のテーマも考えていたんですよ。そのテーマとして話し合っていたのは、サブカルやカルチャーというものの現状はこれで良いのかという疑問だったんです。今は、理系的なものが良しとされている時代です。そうすると、アナログなものだったり、純文学的なもの、まさにカルチャーと呼ばれるようなものはどんどん衰退していく。この流れでいいんだろうかという思いは僕たちが共通して持っているものでした。
いながき:僕は、普段、文章を書いていますが、自分自身でも時代の空気的にも、それは役に立たないものだという自負はありました。でも、それも社会には必要なんだと思って続けてきたのですが、昨今は、より排除されていっている感覚があるんです。カルチャーや哲学というようなものは、短期的に役立つものではありませんが、長い視野で見るべきものじゃないですか。そういう思いがテーマの根本にあります。

いながききよたか(脚本)
――確かに、サブカルはどんどんと肩身が狭くなっているのを感じます。特に今回の、新型コロナウイルス禍ではそれを強く感じました。
後藤:劇中のセリフにも「サブカルは完全に包囲されている」という言葉がありますが、その状況を表現したいと思ったんです。物語の冒頭ではタイムリープの話から入っていますが、最後には、ヴィレヴァンに籠城して、もう絶対に勝てない、負けは確定しているという状態を作り上げました。そして、そこで、好きなものを好きだと叫ぶ。ただ、自分が好きなことを叫ぶだけじゃなく、ほかの人の叫び声にも、「確かにそれもいいよね」とちゃんと耳を傾けた上で自分の「好き」を伝えていく。そうすることで、きっと新しい価値観が(叫んでいる人たちの中に)生まれていく。クライマックスでは、そういうことを伝えたいと話しました。
――真摯なテーマですね。
後藤:ただ、ここが難しいところなんですが、ヴィレヴァンの映画なので、ヴィレヴァンらしい映画にしなくてはダメだというのは大前提としてあるんですよ。ふざけなくちゃダメ。難しいことを匂わせてはダメ。人が引くくらいバカみたいなことを一生懸命にやる。なので、前半ではしっかりとバカをやって、失笑するくらいやりすぎるべきだと思っていました。そして、最後はしっかり締める。それが、結果的に、いろいろなものがごちゃごちゃっと置いてあるヴィレヴァンのお店のような空気になっていると思います。
いながき:そのヴィレヴァン感みたいなのは、めちゃくちゃ出ていると思います。バカだなと思うことをやっているし、その一方でメッセージを臆面もなく、恥ずかしがらずに伝えようとしている。僕は出来上がりを見て間違っていなかったなという気はしています。
――ところで、個性的な役柄を、バラエティ豊かな俳優さんが演じられていましたが、中でも、杉下を拘束する「特高警察」として出演した萩原聖人さんと安達祐実さんの演技は圧巻でした。
いながき:お二人が演じる「特高警察」は、論理的に正しくて、隙がなくて、(杉下らが)押し込まれる展開じゃないと成立しないと思っていたので、過剰なまでにやっていただけて良い形になったと思います。
後藤:僕、最初はそこまでやらなくてもいいと思っていたんですよ。厳しいセリフをいうシーンも多いので、芝居のテンションを抑えめでも、十分、強い表現になるはずだ、と。それに、萩原さんは、『cure』(1997年公開の映画)のときのような「裏で何を思っているんだろう」というような抑えた演技が好きだったので、こんなに叫ばせてしまっていいんだろうかと思っていたんですが、編集作業をしていくうちに、それがぴったりとハマっていました。
いながき:始めは低調なテンションから入って、だんだん激しくなっていくというのが、やっぱりすごいし、良くできていたと思います。
――ありがとうございました。最後に改めて、公開を楽しみにされているファンの方へメッセージを。
後藤:何も考えずに楽しめる映画になっていると思います。一生懸命みんながふざけていて、でもその中に熱意を感じると思いますし、今どう生きるべきかということをしれっと語ってくれているんじゃないかなと思います。見ても損はないはずなんで、ぜひ気軽な気持ちで見にきていただければ。
いながき:本作は、10月23日公開ですが、映画は公開後の3日間の動員数で後々の展開が変わるんです。なので、ぜひ皆さん、23、24、25日はこの映画に来てください。
後藤:3日間しか上映してないっていうことにしますか(笑)?
いながき:そういう気持ちで見にきて欲しいです。翌週もやってたら、それは得したなって思っていただければ(笑)。

映画『リトル・サブカル・ウォーズ 〜ヴィレヴァン!の逆襲〜』
10月23日(金)より全国ロードショー。
(文:嶋田真己/写真:ランラン編集)