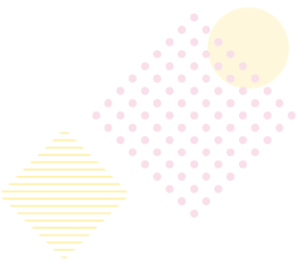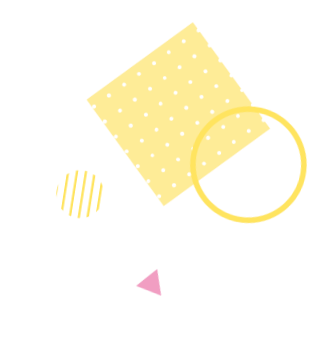取材:記事・RanRanEntertainment/写真・オフィシャル
兵庫県尼崎市で在宅医として働く長尾和宏に密着し、命の駆け引きの現場を記録したドキュメンタリー映画『けったいな町医者』が2月13日(金)より公開される。長尾は、「家に帰りたい」と言っていた患者が自殺したことをきっかけに大病院を辞めて尼崎市で開業し、町医者となった人物。病院勤務医時代に1000人、在宅医となってから1500人を看取った彼は、その経験から、終末期患者への過剰な延命治療に異議を唱えている。今作では、365日24時間いつでも患者の元へ駆けつける長尾の姿に密着。約2カ月に渡り、長尾の姿をカメラに収め続けた毛利安孝監督に、撮影を通して感じたことを聞いた。

――どのようなきっかけがあって、長尾先生のドキュメンタリー作品を制作することになったのですか?
そもそも、長尾先生を知ったのは、高橋伴明監督の映画『痛くない死に方』(2月20日公開)の助監督をさせていただくことになり、その下準備として映画の原作となった先生の著作を読んだことがきっかけでした。そこで、面白い人だな、と。ただ、僕も創造物の世界で仕事をしているので、著作に関してもある種、眉唾なところもあるのではないかとは思ったんです。先生のおっしゃることを全て実践できたら、世界の医療はもっと充実しているはずだろうと、そんなことを思いながら先生にお会いしたら、圧倒的なマンパワーを感じて、非常に興味深かった。それに加え、僕は大阪出身なので、先生が開業している尼崎という町にも予備知識があり、この先生が尼崎で医療をしているということに興味が湧いたんです。そこで、密着をしたら面白いのではないかと思ったのですが、企画の発端としては『痛くない死に方』のDVD特典とすることを考えていました。
――実際に撮影を続けていく中で、長尾先生の印象は変わりましたか?
変わらなかったです。先生は、いい意味でも悪い意味でも、周りから「長尾和宏」という医師を求められていて、長尾先生自身も、一個人ではなく医師としての「長尾和宏」という像を作っていったのだと思います。密着していた間、周りが求める「365日24時間、胸ポケットに携帯を忍ばせた医師」であり続けました。それは先生が裏側を見せなかったというよりは、365日24時間、医師として生きていく覚悟でいるということだと思います。なので、実はこうでしたということはなかったのですが、当初、僕が眉唾っぽいなと思っていた印象からは、「全く眉唾ではなかった」と変わりました。

毛利監督
――劇中には、衝撃的なシーンや心を動かされるシーンも多く映っていました。監督は撮影されていて、どの場面に感銘を受けましたか?
どのシーンというわけではありませんが、やはり全体を通して、長尾和宏という医師が患者さんに向き合っている姿は印象深いものがありました。当然ながら、この作品で写映しているのは、氷山の一角なんですよ。アル中の患者さんもいたり、糖尿病で失明してしまった若い患者さんもいたり、生活保護がなければ生きていく糧のない患者さんもいたり、とにかくさまざまな環境におかれている患者さんの元に長尾先生は診察に行き、励まして、何か彼らの目標を作ろうとしている。その姿は、医師の領分を超えたレベルでのお節介にも見えます。でも、とにかく明日その患者さんがやれること、1週間後までにやれること、1カ月後にやれることを目標にして、約束をするんです。もちろん、お節介を嫌う方もいますが、人間は不思議なもので、そこまで親身になって話をしてくれると、日を重ねるごとに患者さんが段々と打ち解けていって、先生に気持ちを預けていくんですよ。その姿を見て、先生の人間としての凄さを感じました。しかも、先生は、これを毎日やっているんです。自分の気持ちにも状況にも左右されず、毎日です。先生が患者さんに語りかける話は、僕たちと同じ目線の大衆的な話で、お寺の和尚さんがするような高尚な内容というわけではないですが、だからこそたくさんの方に響くんだと思います。
――ナレーションを担当された柄本佑さんは『痛くない死に方』で主人公の河田も演じられています。柄本さんとは、ナレーション収録前にどんなお話をされましたか?
特別に何かを話し合ったということはありませんが、一つだけ注文させていただいたのは、「『痛くない死に方』で演じている役柄としてのナレーションではなく、柄本佑としてやってください」ということでした。それだけお伝えして、読んでもらったら、絶妙に良いんですよ。ドキュメンタリーなので、こちらの思いを押し付けるというよりは、柄本さんの感情のまま読んでいただいたのですが、淡々と読み上げてくださったのが、非常に良かったと思います。

柄本佑
――『痛くない死に方』では、奥田瑛二さんが長尾先生をモデルにした長野浩平を演じています。長尾先生を間近で見ていたからこそ、奥田さんの演技に思うことはありましたか?
ドキュメンタリーの撮影は『痛くない死に方』の撮影が終わった後に行ったので、奥田さんの姿が長尾先生とリンクしたとか、そういったことはなかったです。ただ、長尾先生は(圧にならないようにと)白衣を着ないので、カジュアルな雰囲気を役に投影させるためにも、僕たちスタッフは、奥田さんが着られる衣装は長尾先生に似せようとはしていました。それ以外の立ち振る舞いは奥田さんのオリジナルだと思います。
――では、今、長尾先生に密着された後だからこそ分かる、『痛くない死に方』の中で長尾先生を彷彿とさせるシーンは?
『痛くない死に方』は劇映画ですので、ドラマチックに描かれているシーンも多くあります。例えば、長野がご遺体を抱きしめるシーンなどは、実際には長尾先生はそこまでしないだろうと思っていました。ですが、長尾先生が立ち会う最期の瞬間も、やっぱり劇的なんですよ。(長尾先生は)見送る方に対して、きちんと敬意を持って、愛情を持って…家族の方と対話をしながら、家族の方が悔いを残さないように、「感謝を伝えて」と周りの方たちに声をかけます。その先生のスタンスは、ある種ドラマチックで、映画の中で奥田さんがされていたことに近いことをされているんだなと、改めて感じました。
――なるほど。もちろん『けったいな町医者』『痛くない死に方』をそれぞれ単独で見ても楽しめますが、セットで見ることで、より深く胸に突き刺さるものがあると感じました。
そう言っていただけると本当にありがたいです。このドキュメンタリーを映画として発表しようとなったとき、敬愛する高橋伴明監督の露払いができればいいなという思いからスタートしました。『痛くない死に方』で高橋監督が描かれているのは、医師の成長譚であり、患者側の視点からの物語です。ですが、『けったいな町医者』で描かれているのは、医師側の視点です。リアリティーはこうで、うまくいくこととうまくいかないこともあって、それでも尼崎の街を走り回っている長尾和宏という男がいますということを描いています。この作品で、露払いさせていただければ、本当にありがたいと思っています。
――毛利監督ご自身は、今回の撮影をする前と後で、在宅医療や尊厳死というものに対する考えに変化はありましたか?
多大にありました。まず、先生の著作を読んだときに衝撃を受けて、高橋監督の台本を読んでなるほど、と。老いて死ぬときに、迷惑をかけることになるかもしれないなという負い目が、僕の中にもあったんですが、今、この日本の社会においては、最後まで自分らしく生きて死ぬということをきちんと宣言し、家族の協力を得られれば、そうなるように動けるものなんだと教えていただきました。今回、先生を追いかけてさせてもらった中で、先生の「病院で死ぬよりも俺が看取ってやる」というパワーを持った人柄に触れて、「最後まで生きる」ということについてもきちんと考えるようになりました。家で好きなものを食べて、好きな時間に好きな動きをしながら亡くなりたいという望みは、最後まで自分らしく生きるということだと思います。死ぬことを考えるのではなく、最後の最後まで自分を主張して生きてやろうという考えを持つようになりました。
――今回の作品を通して、見ている方に伝えたいことは?
ある町医者の2019年から2020年初頭の約2カ月間の日々を追いかけただけの作品なので、僕から何かを伝えたいというよりは、見た方が自由に感じ取っていただければと思います。もちろん、(延命治療をすることが正義と考えている医療関係者などから)かなり賛否があるとは思っています。ただ、医者と患者の関係は、人と人なんだと感じていただけると思いますし、「人として生きて、人として人生を謳歌して、人として自分らしく最後まで」ということをやろうとしている人がいることを知ってもらえれば。もちろん、こうした方がいいですよということではありません。病院で死ぬことも、在宅医療も、どちらもいい点も悪い点もある。その上で、この作品が「在宅医療という方法もあるんだ」とか、「ネットで尊厳死って言葉を調べてみようかな」とか、「家族会議で自分の死について考えてみようかな」と何かを考えるきっかけになればいいなと思います。

『けったいな町医者』
出演:長尾和宏
ナレーション:柄本佑
監督・撮影・編集:毛利安孝
制作会社:G カンパニー
配給・宣伝:渋谷プロダクション
2月13日(土)よりシネスイッチ銀座ほか
https://itakunaishinikata.com/kettainamachiisha/
■あらすじ
1995年、病院勤務医として働いていた際に、「家に帰りたい。抗ガン剤をやめてほしい」と言った患者さんが自殺をした。それを機に、阪神淡路大震災直後、勤務医を辞め、人情の町・尼崎の商店街で開業し、町医者となった長尾和宏。病院勤務医時代に1000人、在宅医となってから1500人を看取った経験を元に、多剤処方や、終末期患者への過剰な延命治療に異議を唱える”異端”。
暦を過ぎた長尾は今も、24時間365日、患者の元に駆け付ける。そんな長尾の日常をカメラで追いかけたのは、新型コロナが猛威を振るう直前の2019年末。転倒後、思うように動けなくなり、以前自分の旦那を看取った長尾を往診に呼んだ女性や、肺気腫に合併した肺がん終末期の患者さんなどの在宅医療を追った。リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)と長尾の電話番号を書き残し、自宅で息を引き取ったばかりの方の元に駆けつけた際の貴重な映像も交え、昼夜を問わず街中を駆け巡る長尾の日々を追うことにより、「幸せな最期とは何か」「現代医療が見失ったものとは何か」を問いかける、ヒューマンドキュメンタリー。
※作品ビジュアルのクレジット (C)「けったいな町医者」製作委員会
※柄本佑のアー写 (C)須藤秀之
文・嶋田真己